- з ”з©¶е®Өгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮё
- ж§ӢжҲҗгғЎгғігғҗгғј:
гҒҜгҒ—гӮӮгҒЁ гҒҳгӮҮгғјгҒҳ ж•ҷжҺҲ , жЁ«жқ‘еҚҡеҹә и¬ӣеё«, дҝ®еЈ« 5 еҗҚ, еӯҰйғЁ 4еҗҚ - жүҖеңЁ:
иҮӘ然科еӯҰз·ҸеҗҲз ”з©¶жЈҹ 3 еҸ·йӨЁиҘҝ 5 йҡҺ 506 еҸ·е®Ө (гҒҜгҒ—гӮӮгҒЁ), 502 еҸ·е®Ө (жЁ«жқ‘), 506 еҸ·е®Ө (еӯҰз”ҹ)
з ”з©¶гҒ®иҲҲе‘і
ең°зҗғгӮ„еӨҡгҒҸгҒ®жғ‘жҳҹгҒ®иЎЁеұӨз’°еўғгӮ’иҰҸе®ҡгҒҷгӮӢдёҠгҒ§еӨ§ж°—гӮ„жө·жҙӢгҒҜйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҺдҫӢгҒҲгҒ°зҸҫеңЁгҒ®ең°зҗғең°иЎЁе№іеқҮжё©еәҰгҒҜгҒ гҒ„гҒҹгҒ„ж‘Ӯж°Ҹ15еәҰгҒ§гҒҷгҒҢпјҢгҒ“гӮҢгҒҜеӨ§ж°—гҒ®жё©е®ӨеҠ№жһңгҒЁеӨ§ж°—гғ»жө·жҙӢгҒ®жөҒгӮҢгҒҢзҶұгӮ’еҚ—еҢ—гҒ«ијёйҖҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз¶ӯжҢҒгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҺгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰпјҢеӨ§ж°—зө„жҲҗгӮ„еӨ§ж°—гғ»жө·жҙӢгҒ®жөҒгӮҢгҒҢеӨүеҢ–гҒҷгӮҢгҒ°иЎЁеұӨз’°еўғгӮӮеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢпјҢгҒқгҒ®гғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гҒҜеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒҜгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸпјҢеӨүеҢ–гҒ®дәҲжғігҒҜжңӘгҒ гҒ«гҒҹгӮ„гҒҷгҒҸгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“пјҺгҒҫгҒ—гҒҰпјҢең°зҗғиЎЁеұӨз’°еўғгҒҢз”ҹе‘ҪгӮ’иӮІгӮҖжғ‘жҳҹгҒЁгҒ—гҒҰйҒҺеҺ»45е„„е№ҙй–“гҒ®й•·гҒҚгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰпјҢе…ЁзҗғеҮҚзөҗгҒӘгҒ©гҒ®дәӢиұЎгӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҒӨгҒӨгӮӮпјҢгҒӢгҒӘгӮҠе®үе®ҡгҒ«еӯҳеңЁгҒ—гҒҲгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜй©ҡз•°гҒЁгҒ„гҒҶгҒ№гҒҚгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠпјҢгҒқгҒ®е®үе®ҡжҖ§гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дҝқгҒҹгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒӢгҒҜгҒҫгҒ гӮҲгҒҸзҗҶи§ЈгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„е•ҸйЎҢгҒ§гҒҷпјҺең°зҗғгҒҠгӮҲгҒіжғ‘жҳҹеӨ§ж°—科еӯҰз ”з©¶е®ӨгҒ§гҒҜпјҢең°зҗғгӮ’гҒқгҒ®пј‘гҒӨгҒЁгҒҷгӮӢжғ‘жҳҹеӨ§ж°—дёҖиҲ¬гҒ®ж°—иұЎгӮ„ж°—еҖҷгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’ж”Ҝй…ҚгҒҷгӮӢзҗҶгҒ®и§ЈжҳҺгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҺ
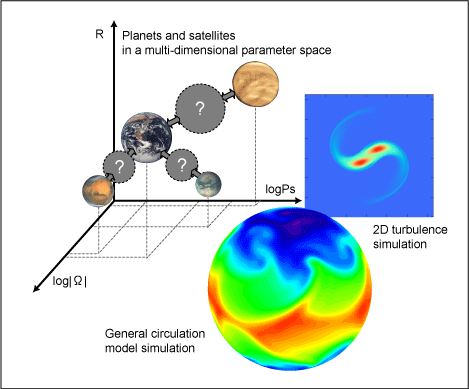
1. жғ‘жҳҹж°—иұЎеӯҰгғ»ж°—еҖҷеӯҰгҖҖпҪһжғ‘жҳҹеӨ§ж°—гғ»иЎЁеұӨз’°еўғгҒ®еӨҡж§ҳжҖ§гҒ«й–ўгҒҷгӮӢз ”з©¶пҪһ
еӨӘйҷҪзі»еҶ…гҒ®ең°зҗғеһӢжғ‘жҳҹ (ең°зҗғгғ»йҮ‘жҳҹгғ»зҒ«жҳҹ) гҒ®еӨ§ж°—йҒӢеӢ•гӮ’жҜ”гҒ№гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁпјҢйҮ‘жҳҹгҒ§гҒҜгӮ№гғјгғ‘гғјгғӯгғјгғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢжғ‘жҳҹгӮ’4ең°зҗғж—ҘгҒ§дёҖе‘ЁгҒҷгӮӢйҖҹгҒ„жқұйўЁгҒҢеҗ№гҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгӮҠпјҢзҒ«жҳҹгҒ§гҒҜе°ҸиҰҸжЁЎгҒӘгӮӮгҒ®гҒӢгӮүжғ‘жҳҹе…ЁдҪ“гӮ’иҰҶгҒҶгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒҫгҒ§ж§ҳгҖ…гҒӘиҰҸжЁЎгҒ®гғҖгӮ№гғҲгӮ№гғҲгғјгғ гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹгӮҠгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹпјҢең°зҗғгҒ§гҒҜиҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„дёҚжҖқиӯ°гҒӘеӨ§ж°—зҸҫиұЎгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҺгҒҫгҒҹпјҢеӨӘйҷҪзі»еӨ–гҒ«зҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжғ‘жҳҹгҒ®иЎЁеұӨз’°еўғгғ»еҫӘз’°ж§ӢйҖ гҒҜеӨӘйҷҪзі»еҶ…жғ‘жҳҹгҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјҺгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘең°зҗғгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢеӨ§ж°—зҸҫиұЎгҒҢгҒ©гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гҒ§зҷәзҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢпјҢгҒҫгҒҹгҒӘгҒңгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҸҫиұЎгҒҜең°зҗғгҒ§гҒҜиҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢпјҢгҒ•гӮүгҒ«гҒҜеӨӘйҷҪзі»еӨ–гҒ®гҒҫгҒ иҰӢгҒ¬жғ‘жҳҹгҒ®еӨ§ж°—еҫӘз’°гҒҜгҒ©гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҒҲгӮӢгҒ®гҒӢпјҢгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹе•ҸйЎҢгӮ’зҗҶи«–зҡ„гғ»ж•°еҖӨзҡ„гҒ«з ”究гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷ.
2. жғ‘жҳҹйҖІеҢ–еӯҰгҖҖпҪһз”ҹеӯҳеҸҜиғҪжғ‘жҳҹгҒ®еҪўжҲҗгҒЁйҖІеҢ–гҒ«й–ўгҒҷгӮӢз ”з©¶пҪһ
ең°зҗғгҒ«гҒҜжө·гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰз”ҹзү©гҒҢгҒҜгҒігҒ“гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢпјҢгҒқгҒ®гҒҠйҡЈгҒ®йҮ‘жҳҹгҒЁзҒ«жҳҹгҒҜгҒқгӮҢгҒһгӮҢзҒјзҶұгҒЁй…·еҜ’гҒ®з’°еўғгҒ§жө·гҒҜгҒӘгҒҸз”ҹзү©гӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгҒҫгҒҷпјҺгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹжғ‘жҳҹиЎЁеұӨгҒ®йЎ”гҒӨгҒҚ (з’°еўғ) гҒ®йҒ•гҒ„гҒҜпјҢеӨӘйҷҪж”ҫе°„еҠ зҶұгҒ®еј·гҒ•пјҢеӨ§ж°—гғ»жө·жҙӢгҒ®иіӘйҮҸгҒЁзө„жҲҗпјҢжғ‘жҳҹгҒ®иҮӘи»ўйҖҹеәҰгҒЁиҮӘи»ўи»ёеӮҫж–ңи§’пјҢгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢпјҢгҒӘгҒӢгҒ§гӮӮеӨ§ж°—иіӘйҮҸгҒЁзө„жҲҗгҒ®йҒ•гҒ„гҒҢжғ‘жҳҹиЎЁеұӨз’°еўғгҒ®еӨҡж§ҳжҖ§гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷдё»иҰҒгҒӘеҺҹеӣ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҺеӨ§ж°—гғ»жө·жҙӢгҒҜжғ‘жҳҹеҪўжҲҗгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«еҪўжҲҗгҒ•гӮҢпјҢеҪўжҲҗеҫҢгҒҜеӨ§ж°—гҒҢе®Үе®ҷз©әй–“гҒ«жөҒеҮәгҒ—гҒҹгӮҠпјҢеӣәдҪ“жғ‘жҳҹгҒЁзү©иіӘдәӨжҸӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨүеҢ–гҒ—гҒҫгҒҷпјҺгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰпјҢжғ‘жҳҹиЎЁеұӨз’°еўғгҒ®еӨҡж§ҳжҖ§гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜпјҢжғ‘жҳҹеҪўжҲҗйҒҺзЁӢгҒӢгӮүгҒқгҒ®еҫҢгҒ®ең°иіӘеӯҰзҡ„жҷӮй–“гӮ№гӮұгғјгғ«гҒҫгҒ§гӮӮеҗ«гӮҒгҒҰпјҢеӨ§ж°—гҒ®иіӘйҮҸгҒЁзө„жҲҗгҒ®йҖІеҢ–гӮ’и§ЈжҳҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷпјҺзҗҶи«– (зҸҫиұЎгҒ®ж•°зҗҶзү©зҗҶзҡ„гҒӘиЁҳиҝ°)гғ»ж•°еҖӨе®ҹйЁ“ (еҚҳзҙ”еҢ–гҒ—гҒҹжғ‘жҳҹиЎЁеұӨз’°еўғгғўгғҮгғ«)гғ»иҰіжё¬ (жҺўжҹ»ж©ҹгғ»ең°дёҠжңӣйҒ йҸЎ) гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжүӢж®өгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰпјҢжғ‘жҳҹиЎЁеұӨз’°еўғгҒ®еҪўжҲҗгҒЁйҖІеҢ–гӮ’ж”Ҝй…ҚгҒҷгӮӢзҗҶгҒ®и§ЈжҳҺгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҺ
дё»гҒӘз ”з©¶гғҶгғјгғһ
ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҶгғјгғһгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷ.
- еӨ§ж°—еӨ§еҫӘз’°гғўгғҮгғ«гӮ’з”ЁгҒ„гҒҹжғ‘жҳҹеӨ§ж°—еӨ§еҫӘз’°гҒ®з ”究 (зҒ«жҳҹ, ең°зҗғ, йҮ‘жҳҹ, еӨ–жғ‘жҳҹ, зі»еӨ–жғ‘жҳҹ)
- з°Ўз•ҘгғўгғҮгғ«гӮ’з”ЁгҒ„гҒҹеӨ§ж°—зҸҫиұЎзҙ йҒҺзЁӢгҒ®з ”究
- йҮ‘жҳҹжҺўжҹ»ж©ҹгҖҢгҒӮгҒӢгҒӨгҒҚгҖҚгғҮгғјгӮҝи§Јжһҗ
- зҒ«жҳҹзқҖйҷёж©ҹжҗӯијүз”Ёж°—иұЎжё¬еҷЁгҒ®й–ӢзҷәгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ
гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжӣҙж–°ж—ҘгҖҖ2025.6.25
 зҘһжҲёеӨ§еӯҰ
зҘһжҲёеӨ§еӯҰ зҗҶеӯҰз ”з©¶з§‘гғ»зҗҶеӯҰйғЁ
зҗҶеӯҰз ”з©¶з§‘гғ»зҗҶеӯҰйғЁ йғҪеёӮе®үе…Ёз ”з©¶
йғҪеёӮе®үе…Ёз ”з©¶ жғ‘жҳҹ科еӯҰз ”з©¶
жғ‘жҳҹ科еӯҰз ”з©¶ жө·жҙӢеә•жҺўжҹ»
жө·жҙӢеә•жҺўжҹ»